「職場を辞めたい。
でも、いつ言えばいい?」
そんな悩みを抱える
看護師は多いですよね。
特にママナースは
家庭との両立もあるため
タイミングが命です。
この記事では、円満に
退職できる時期を解説。
私の「怒涛の」退職談も
赤裸々に書きました。
読むことでトラブルを避け、
笑顔で次のステージへ
向かえるはずですよ。
この記事の結論
看護師の退職時期は
「3ヶ月前」が理想的!
現場の調整を考えて
早めに相談しましょう。
もくじ
退職の切り出しは3ヶ月前がベストな理由
看護師の世界では、
2〜3ヶ月前の報告が
暗黙のルールです。
法律上は2週間前でも
辞められますが、
現実は厳しいもの。
現場の事情
- シフト作成の都合がある
- 後任の募集に時間がかかる
- 業務の引継ぎを丁寧にする
これらを総合して考えると、
3ヶ月の余裕があるのが
お互いに一番安心です。
【実録】公務員合格で「怒涛の退職劇」
実は私、23歳の時に
かなり無茶な転職を
経験しました。
目指したのは公務員。
でも合格発表があったのは、
採用の「1ヶ月前」でした。
私の失敗体験
- 発表まで言えない不安
- 直後の報告による気まずさ
- 有給消化はまさかのゼロ
- 退職当日は深夜明け勤務
規則は守りましたが、
シフト変更も間に合わず
まさに怒涛の毎日。
深夜明けのボロボロな体で
挨拶回りをして退職。
記憶が曖昧なほど必死で、
心残りが多かったです。
失敗しない!退職までの3ステップ
私のようなハードな
状況にならないための、
正しい手順です。
1. 直属の上司に相談
まずは師長さんに
「ご相談があります」と
アポを取りましょう。
2. 意思を明確に伝える
「検討中」ではなく
「〇月末で辞める」と
断定して伝えます。
3. 退職届の提出
合意が得られたら、
規定の期限までに
書類を提出します。
最後は笑顔で!挨拶に喜ばれる菓子折り
退職日が決まったら、
部署へ配る菓子折りの
準備も進めましょう。
【近日公開!】私が実際に職場で贈って
喜ばれたものや、
もらって嬉しかったお菓子を
現在まとめています。
喜ばれたものや、
もらって嬉しかったお菓子を
現在まとめています。
リアルに評判が良かった
厳選リストを公開予定です。
お楽しみに🌷
まとめ|余裕を持って新しいステージへ
退職を伝えるのは
とても勇気がいります。
でも、早めに動けば
有給もしっかり取れて、
笑顔で卒業できますよ。
私の失敗談を
反面教師にして、
後悔のない退職を!
今日からできること
まずは職場の就業規則を見て、
退職の規定期間を
こっそり確認しましょう!
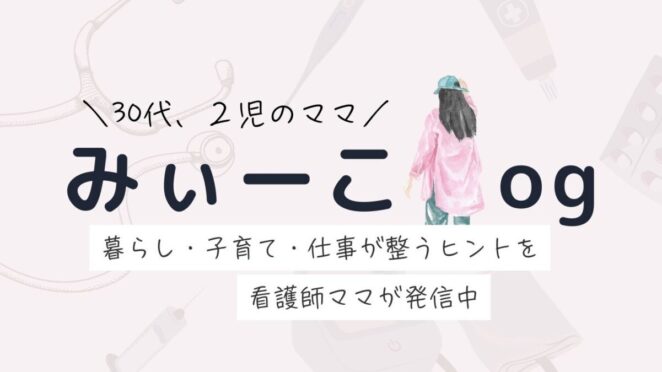



コメント